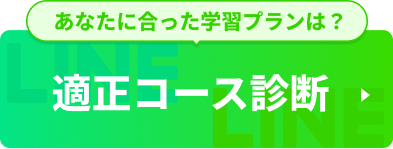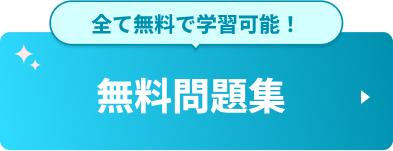CSSコードを「もっと分かりやすく」する魔法:コメントとコメントアウト
Webサイトのデザインを整えるCSS。コードが複雑になるにつれて、こんな悩みはありませんか?
- 「このCSS、何のために書いたんだっけ…?」
- 「一時的にこのスタイルを無効にしたいけど、消すのは怖いな…」
そんな時、あなたのCSSコードを救うのが「コメント」と「コメントアウト」です。これらはHTMLやJavaScriptと同様に、CSSでも非常に重要な役割を果たします。この記事では、CSSにおけるこれら二つの機能の正しい使い方を、実践的な視点から徹底解説します。
CSSにおける「コメント」と「コメントアウト」の基本

「コメント」とは?:スタイルシートに「注釈」を付与する
「コメント」とは、CSSのスタイルシート内に記述する「注釈」や「説明文」そのものです。ブラウザがCSSを解釈する際には完全に無視されるため、表示や動作に影響を与えることはありません。主に以下の目的で活用されます。
-
- スタイルの意図の明確化
なぜこのプロパティを設定したのか、このセレクタの目的は何か、といった「設計思想」を説明します。 - 複雑な記述の補助
特に複雑なセレクタの組み合わせや、特定のブラウザ向けハック、計算式など、一見して理解しにくい部分に補足情報を加えます。 - 未来の自分やチームへの伝言
後からコードを見直す際や、他のデザイナー・開発者がコードを理解する際の貴重な手がかりとなります。
- スタイルの意図の明確化
コメントの基本的な記述方法
CSSのコメントは、/*で始まり、*/で終わります。この記号で囲まれた範囲のテキストがすべてコメントとして認識されます。
/* これはCSSのコメントです。ブラウザには表示されません。 */
body {
/* 背景色を定義 */
background-color: #f0f0f0;
}
/*
複数行にわたる詳細な説明や、
スタイルシートの大きなセクションの概要を記述する際に有用です。
例:
▼▼ グローバルヘッダーのスタイル定義 ▼▼
*/
header {
padding: 20px;
}
/* ▲▲ グローバルヘッダーのスタイル定義 ▲▲ */
多くのコードエディタでは、「Ctrl+/」(Windows)や「Cmd+/」(Mac)のショートカットキーで簡単に行や選択範囲をコメントアウトできます。
「コメントアウト」とは?:CSSルールを「一時的に無効化」する行為
「コメントアウト」とは、既存のCSSコードを「コメント」の形式に変換することで、一時的にそのスタイルルールが適用されないようにする「行為」を指します。これは、CSSのデバッグやデザインの微調整において非常に有効な手段です。
コメントアウトの主な活用場面
- デバック作業
特定のスタイルがレイアウト崩れや予期せぬ表示の原因となっている場合、そのプロパティやスタイルブロックを一時的にコメントアウトし、問題の切り分けを行います。 - デザインの比較検討
複数のデザイン案やプロパティの値を試す際、一時的に現在のスタイルを無効にして、異なるパターンを比較検討したい場合に役立ちます。 - 未完成・期間限定スタイルの管理
まだ適用準備ができていないスタイルや、特定の期間だけ表示するキャンペーンバナーなどのスタイルを、一時的に非表示にしておくことができます。
/* メインのフォントサイズ */ body { font-size: 16px; /* color: #333; ← この行はコメントアウトされているため、適用されません */ } /* 以下のスタイルは現在テスト中です。 .test-element { border: 1px solid red; background-color: yellow; }*/
良いコメント・悪いコメント:スタイルシートの可読性を高めるために

良いコメントのポイント
- 「なぜ」を説明する
コードが「何をしているか」はCSS自体を見れば明らかです。コメントでは「なぜそのプロパティを選んだのか」「このスタイルが必要な背景は何か」といった設計意図を記述しましょう。
例
/* IE11でflexboxのバグを回避するための記述 */
- 複雑な記述の補足
特に複雑なセレクタの指定や、特定のブラウザ向けハック、計算式など、一見して理解しにくい部分に補足説明を加えます。 - セクションの明確化
大規模なCSSファイルでは、主要なセクション(例: リセットCSS、共通スタイル、各コンポーネントのスタイルなど)の開始と終了をコメントで明示すると、全体構造の把握が容易になります。
例
`/* ========== グローバルナビゲーションスタイル開始 ========== */ - 注意点や改善点の記録
将来の自分や他の開発者への申し送り事項、一時的な対応であること、将来的な改善点などをメモとして残します。
避けるべきコメントの例
-
- コードを見ればわかることの繰り返し
/* 背景色 */ background-color: #fff;のような、冗長なコメントは避けましょう。 - 古い情報や誤った情報
コードを修正した際は、関連するコメントも必ず更新してください。古いコメントは混乱やバグの原因となり得ます。 - 過剰なコメントアウト
デバッグなどで一時的にコメントアウトしたコードは、作業が完了したら削除するか、バージョン管理システム(Gitなど)で適切に管理しましょう。不要なコードが残っていると、スタイルシート全体の可読性が著しく低下します。 - コメントの入れ子
CSSのコメント構文では、コメントの中にさらにコメントを入れることはできません。これは構文エラーの原因となるため、絶対に避けましょう。
- コードを見ればわかることの繰り返し
まとめ:コメントとコメントアウトを駆使して、より洗練されたCSSを
今回は、CSSにおける「コメント」と「コメントアウト」の正しい使い方、そしてスタイルシートの品質を高めるためのコメントの活用術を解説しました。
-
- コメント:スタイルシートに「注釈」を付与し、設計意図や背景を伝えるためのもの。
- コメントアウト:コードを「一時的に無効化」する行為。デバッグやテストに活用。
この二つの機能を適切に使い分けることで、あなたのCSSコードは格段に分かりやすくなり、未来の自分やチームメンバーとのコミュニケーションも円滑になります。ぜひ今日から実践し、よりメンテナンス性の高いWebデザインを目指しましょう。
「忍者CODE」は未経験からでもWeb制作のプロを目指せるオンラインスクールです。
-
- 忍者CODEのWeb制作コースでは、
- 業界最安級の料金でしっかりとスキルを習得できるWeb制作コース・独学プラン
- スキルの習得後に必ず副業案件を紹介してもらえるWeb制作コース・副業支援プラン
- 転職サポートのプロから転職支援が受けられるWeb制作コース・転職支援プラン
の3つのプランから選べます。
学習コースに関するご相談や学習後のキャリアに関するご相談などについては、
こちらの無料メンター相談にて受け付けておりますので、お気軽にお申込みください!また、CSS初学者が無料で基礎を学べる CSSの入門講座や無料でCSSの問題に挑戦できる CSSの無料問題集も非常に好評です!